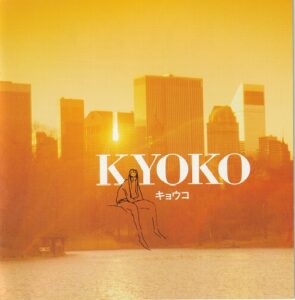
映画「KYOKO」オリジナルサウンドトラック
(1995-1996年)
1.エスペランサ /ファビエル・オルモ
2.ラ・カチンバ / NG ラ・バンダ
3.ポルタル(キョウコ バージョン)/ NG ラ・バンダ
4.ラ・コンパルサ/ NG ラ・バンダ
5.愛しのカマレラ / トニー・カラ
6.ラス・クワトロ・パローマス / セイナイダ・アルメンテロス
7.ラグリマス・ネグラス / セイナイダ・アルメンテロス
8.ノソートロス / ファビエル・オルモ
9.ボニート&サブロッソ/トニー・カラ
10.町に出て酒(ラム)を飲もう/ トニー・カラ
11.シボネイ/ ファビエル・オルモ
12.ラ・ブルッハ(キョウコ バージョン)/ NG ラ・バンダ
アルバムのブックレットより
映画『KYOKO』の音楽は、脚本の進行と変化に従って、そのコンセプトがどんどん変わっていった。キューバには、無数のきれいな曲があり、新旧入り乱れて数えきれないほどのバンドがあり、音楽の種類もすぐには理解できないほど多い。
私は、そういう中から、“キョウコのテーマ”となるべき一曲をまず選ばなければならなかった。キューバの楽由の中で、最も有名なのは、エルネヌト・レクオーナの『シボネイ』である。映画の持つあるムードを表現するために、テーマ由は映画館を出る時に口ずさめるくらい親しみやすく、かつ切なく、そして美しく、キューバらしい高揚感もなくてはいけない。
NGラ・バンダのユニットを使って、1995年の2月、高岡早紀のダンスレッスンの合間に、『シボネイ』の録音を始めた。歌手のイメージは、1930〜40年代の超人気バンド、レクオーナ・キユーバンボーイズのすばらしいボーカリスト、アルベルト・ラバリアティだった。
最初に予定していた歌手は、ロベルト・ファスというグループの、ロリートとアルマンディートというおじいさんのデユオだ。ファスというのは、キユ-バを代表するボレロ歌手で、ロリートは、ファス本人とはるか昔からコンフント・カシーノというバンドでデュオをうたっていた。ファス本人が死んでも、コンフント・ロベルト・ファスというバンドは残り、ファスによく似た声の持ち主ということでアルマンディートが加入したのだった。
私は、二人の老人の美しい声が好きで、ムラカミズのキューバン・カンツォーネにも起用した。だが、二人の声は、『シボネイ』|には向かなかった。エルネスト・レクウォーナはもともとクラシックの作曲家で、『シボネイ』|は、特別に厳密なメロデイラインを持っていたのだ。
深夜のスタジオに、何人もの歌手を呼んで、うたわせたが、誰もラバリアティのようにはうたえなかった。
絶望して、「でも、キユーバだからきつといるはずだ」と気をとり直し、あらゆるビデオをテレビ局で見せて貰ったりして、必死で捜した。
そうやって、十三番目に、スタジオにやって来たのが、ファビエル・オルモだった。
ファビエルは、オルケスタ・アラゴンのサイド・ボーカルだったホセ・“ペペ”・オルモの息子で、国立合唱隊の一員だった。
合唱隊の公演が終わるのを、会場の出口で待ち、そのまま車に乗せてスタジオに来てもらった。電話が通じないし、スタジオの予約時間もあるので、そうするしかなかったのだ。
ファビエルは、ほとんどリハも行なわないまま、他の歌手達が2、3時間も苦闘して結局うたえなかった『シボネイ』を、たった5分で、完壁にうたった。
私は、よろこび、興奮して、「君の声が映画にのって、全世界で流れるんだ」と言つたが、ファビエルは、ポカンとして、「何のこと?」と、いう顔をしていた。それが、フアビエルとの出会いだった。
ファビエルの声があまりにもすばらしかったので、オリジナルを使うはずだった挿入曲の『エスペランサ』と『ノソートロス』も、彼の声で録り直すことにした。二曲分の演奏を依頼するために、ハバナから二時間の田舎町で公演中の、オルケスタ・アラゴンに会いに行った。アラゴンは、創立五十年を迎える伝説のオルケスタである。リチャード・エグエスとラファエル・ライという二人の天才が、アラゴンをつくり、レパートリーは、録音したものに限つても800曲を越えるという。
現在は、ラファエル・ライの息子が、リーダーで、中南米を中心に演秦活動をしている。そのアラゴンが、珍しくキューバにいたのだ。停電中で真暗な、田舎町のレストランで、「映画のためにレコーディングしてくれ」とラフアエル・ライ・Jrに、頼んだ。
「おお、お前がムラカミか、若いんだな」とジュニアは、あっさりと仕事を受けてくれた。
そして、『エスペランサ』が生まれた。あっという間のレコーディングだった。終わって、みんなにキャッシュでギャラを払うと、「よし、これで酒を買って女のところへ行くぞ」と叫ぶ声が聞こえたりした。
新録音の『エスペランサ』があまりによくできたので、他の挿入曲も、新しくレコーディングすることにした。セプテート・ナショナルと、ディレクターはパンチョ・アマト、そして、歌はセナイダ・アルメンテロス。セプテート・ナショナルは、偉大なるイグナシオ・ピニェーロが作った、これも伝説のバンド。パンチョは、元アダルベルト・アルヴァレスのバンドにいた天才トレスギター奏者、そして、セナイダは、高岡早紀がダンスレッスンをしたコンフント・フォークロリコ・ナショナルの、専属歌手だった。その組み合わせで、『ラス・クアトロ・パロマス』と、『ラグリマス・ネグラス』を、録った。
結局、映画には、新旧のキューバを代表する曲を使うことになった。
アラゴン、イグナシオ・ピニエーロ、べニー・モレ、 トリオ・マタモレス、レクォーナ、そして、NGラ・バンダとホセ・ルイス・コルテス。
これらの音楽は、映画『KYOKO』を支え、救った。
特に、『エスペランサ』は、たぶん、私の人生でもっとも大切な曲の一つになるだろうと思う。
5. Dec.1995 村上龍
Produced By : Ryu Murakami
Directed By : José Luis Cortés (M2,3,4,5.9,10,11,12), Rafael Lay Jr. (M1,8), Franclsco Amat (M6,7)
Recorded & Mixed By : Rolando Santos(M1,4,6,7,8,11), Sinpachirou Kawade(Music lnn)(M2,3)
Recorded By : Rolando Santos, Ramón Alom Suarez(M5,9,10)
Mixed By : Shinji Nishikubo(M5,9), Shinpachirou Kawade(M10)
Mastering Engineer : Thoshiya Horiuchi